「最近の生徒たち、何を考えているんだろう…」
先生という仕事をしていると、生徒との間に見えない壁を感じて、ふと孤独になる瞬間、ありませんか。熱意はあるのに、それがうまく伝わらないもどかしさ、僕もよくわかります。
でも、もしかしたら、僕たちが良かれと思ってやっている指導が、少しだけ方向性がずれているのかもしれません。
そこで今回は、僕自身が読んで「これは!」と思った心理学の知見を、皆さんと共有させてください。科学的な視点を取り入れることで、生徒指導の新しいヒントが見つかるかもしれません。
まずは前提:なぜ僕たちの「熱意」は空回りするのか?
本題に入る前に、少しだけ前提の話をさせてください。僕たちが「良かれと思って」やる指導が空回りする背景には、いくつかの心理的な「壁」があったりします。
その一つが、有名な「返報性の原理」です。
“人間文化のなかで、最も広範囲に存在し、最も基本的な要素となっている規範の一つに返報性のルールがある。このルールは、他者から与えられたら自分も同じようなやり方で相手に返すように努めることを要求する。”
(『影響力の武器[第三版] なぜ、人は動かされるのか』より)
リンク
これは、心理学者ロバート・チャルディーニが提唱した法則でして、ざっくり言えば「人は誰かから何かを与えられると、お返しをせずにはいられない」という心理のことですね。
これを生徒指導に置き換えると、僕たちがまず生徒に何かを「与える」こと、例えば、彼らの話をただ聞く、小さな良い変化を認めてあげる、といったことが重要になってくるわけです。言われてみれば当たり前ですけど、忙しい毎日だとうっかり忘れがちですよね。
1. 自己肯定感のスイッチは「学業以外の物差し」にある
さて、本題です。一つ目は、思春期の生徒を扱う上で避けて通れない「自己肯定感」の問題。作家の橘玲氏が言うように、生徒の問題行動は、傷ついた自尊心を守るためのSOSである可能性も考えられます。
“ひとは攻撃されれば反撃するし、自尊心を守るためにはどんなことでもする。”
(『バカと無知―人間、この不都合な生きもの―』より)
リンク
では、どうすれば彼らの自己肯定感を育めるのか。ここで少し変わった角度からのデータを紹介させてください。
“男性においては筋力の強さと自尊心の高さが比例する=筋力を増やせば自尊心も向上する ということが言えると思います。”
(『超筋トレが最強のソリューションである 筋肉が人生を変える超科学的な理由』より)
リンク
もちろん、これは「みんなで筋トレしよう」という話ではありません。この話の本質は、「学業」という一つの物差しだけで生徒を評価しないことの重要性を示唆している、と僕は考えています。
例えば、勉強は少し苦手でも、
- 誰よりも絵が上手い
- いつも友人に囲まれていて、誰にでも優しい
- 部活動の朝練に、一日も休まず参加している
こうした、その生徒が「輝ける場所」を見つけ、そこを具体的に承認してあげること。それが、生徒が自分自身を肯定するための、何よりのエネルギーになるのではないでしょうか。
2. 「怠惰」に見える生徒が発する”SOS”と、その対策
「やる気がない」「集中力がない」。そう見える生徒に対し、僕らはつい「怠けている」と思ってしまいがちです。しかし、デヴォン・プライス氏の研究(R)は、その見方に警鐘を鳴らしています。
“集中できない、疲れた、やる気が出ない、など怠惰な気分が起こるのは、実は私たちの身体や脳が休息を切実に必要としているからだ。”
(『「怠惰」なんて存在しない 終わりなき生産性競争から抜け出すための幸福論』より)
リンク
特に真面目で完璧主義な生徒ほど、失敗への不安から無意識にブレーキをかけてしまい、動けなくなっているケースは少なくありません。なんとも、皮肉な話っすね。
が、ここには希望もありまして、対策としてデヴォン・プライス氏は「自己決定権」を与えることを提案しています。
“自分の人生を自分で決める権利を奪われると、やる気を出す理由はなくなり、頑張る意味も見出せない。”
(同上)
「AとB、どっちのやり方でやってみる?」
「提出日、いつなら君のペースで間に合いそうかな?」
このように、教員が一方的に指示するのではなく、生徒自身に「選択」と「決定」の機会を少しでも与えること。これが、彼らの主体性を引き出す上で、非常に効果的なアプローチだと言えるでしょう。
3. 挑戦できる教室の土台、「心理的安全性」
最後に、クラス運営の土台となる「心理的安全性」という考え方を紹介します。これはGoogleの研究で注目された概念ですね。
“「心理的安全」はチームに対する信頼感のことで、ざっくり言えば「どんなにヒドい失敗や恥ずかしいミスをしても、この仲間ならバカにもされないし適切に助けてくれるだろう」と思える感覚を意味します。”
(『科学的な適職』より)
リンク
この「失敗しても大丈夫」という感覚は、学校の教室にこそ必要だと、僕は強く思います。
失敗を恐れる環境では、生徒は挑戦しなくなります。手を挙げなくなり、質問しなくなり、ただ静かに時間が過ぎるのを待つだけになってしまう。
僕たち教員がすべきことは、失敗を責めることではなく、むしろ「よく挑戦したね!」と、その一歩踏み出した勇気を称えることなのかもしれません。失敗は、学びの絶好の機会でしかありませんから。
4. 才能のスイッチ:「比較優位」という視点
「あの子には才能があるが、この子にはない」。僕たちは無意識にそう考えてしまいがちですが、才能の本質は少し違うのかもしれません。鈴木祐氏の『天才性が見つかる 才能の地図』では、「比較優位」という面白い考え方が紹介されています。
“君にとっては苦手で嫌いなことでも、周囲とのバランスによっては「優れた能力」になりえるわけだ。”
(『天才性が見つかる 才能の地図』より)
リンク
ざっくり言えば、その子の絶対的な能力ではなく、クラスやチームの中で、相対的に得意なことが「才能」になる、ということです。
例えば、全員が発言したがるクラスでは、「人の話を静かに聞ける子」の価値が上がります。逆に、静かなクラスでは、「最初に発言できる子」が貴重な存在になる。
この視点を持つと、すべての子に「才能」を見出すことができるようになります。面白いですよね。
まとめ
長くなりましたので、最後に要点をまとめます。
- まずは生徒の話を最後まで聞いてみるのはいかがでしょうか。 アドバイスは、その後でも遅くありません。
- 勉強以外の「物差し」で、生徒の輝ける場所を見つけて承認してみる。
- 「怠惰」はSOSのサインと捉え、生徒に「休む許可」と「自己決定権」を与えてみる。
- 失敗を責める代わりに、「ナイスチャレンジ!」と声をかける文化を作ってみる。
いずれにせよ、生徒指導に唯一の正解はないですが、科学的な視点を持つことで、僕たちの引き出しが増えるのは確かでしょうな。
この記事が、皆さんの明日からの実践の、何か少しでもヒントになれば嬉しいです。

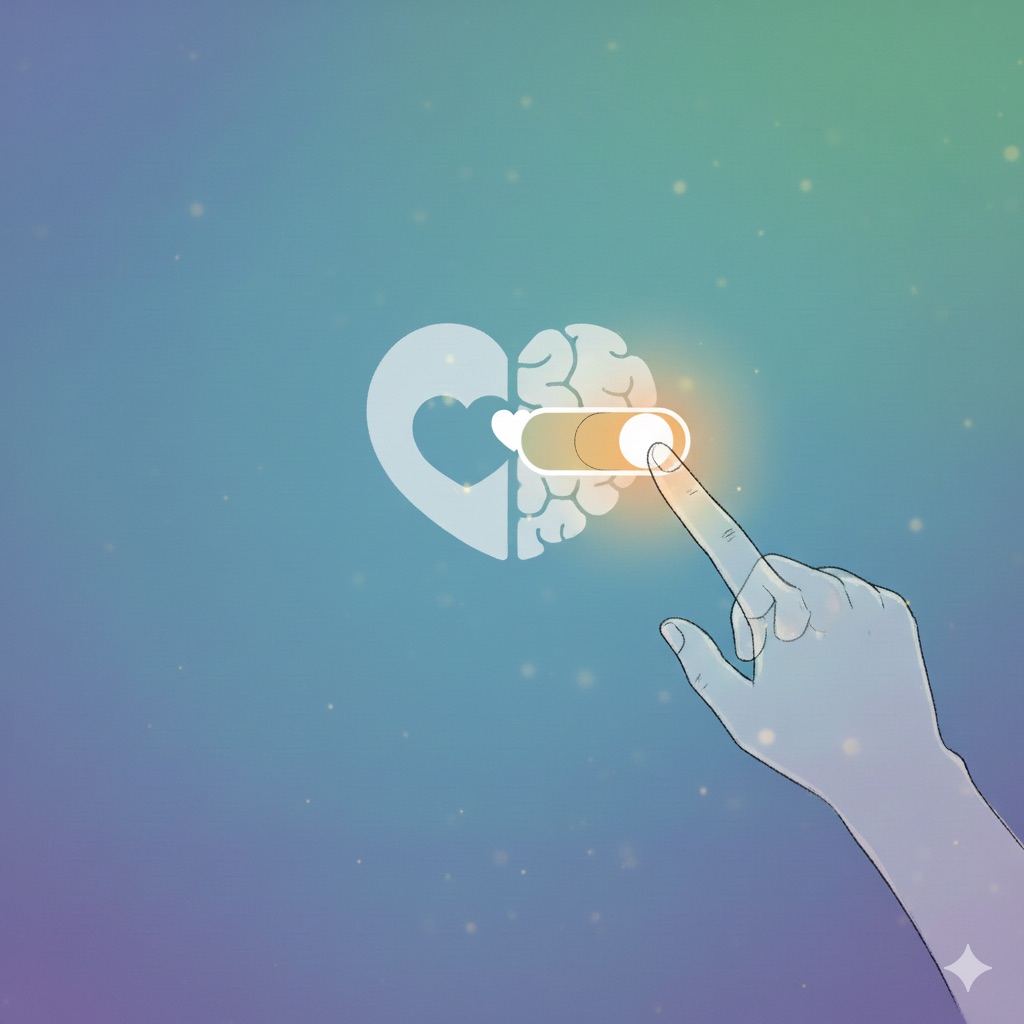
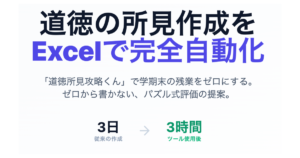
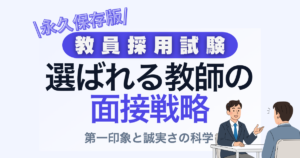



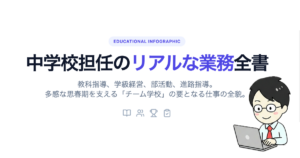


コメント